






2025年4月から新築住宅で省エネ基準への適合が義務化されます。ZEH基準は省エネ基準を上回る性能が求められますが、どのような違いがあるのでしょうか。
ZEHとは何か概要やZEHの4つの基準について押さえたうえで、省エネ性能に関わる他の基準にも触れていきます。
CONTENTS
ZEH(ゼッチ)とは、「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」を略した言葉です。年間のエネルギー消費量から年間で創り出したエネルギー量を引いた収支がゼロ以下になる住宅をいいます。
ZEHでは、断熱性能や省エネ性能の向上を図るとともに、太陽光発電などでの再生可能エネルギーシステムを導入してエネルギーを創り、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロ以下にします。一次エネルギー消費量とは、建物で使われている冷暖房や換気、給湯、照明の各設備の消費エネルギー量から、太陽光発電システムなどによって生み出すエネルギー量を引いたものをいいます。
ZEHには3つの必要要素があり、「高断熱」「省エネ」「創エネ」です。
従来の住宅では、夏に気温が上昇すると室内が暑くなり、冬に気温が低下すると室内が寒くなることから、冷暖房に多くのエネルギーを必要としました。ZEHでは、屋根や壁、床へ断熱材を使用し、窓のサッシやガラスを断熱性・気密性の高いものにすることで高断熱化を図り、室内外に熱を伝えにくくします。
高断熱化により、冷暖房によるエネルギー消費量を削減するとともに、住宅内の温度が一定に保たれやすくなり、快適に暮らしやすい住まいになります。
省エネとは、エネルギー使用量の少ない、つまりエネルギー効率のよい設備機器を使用し、省エネルギー化を図ることをいいます。
ZEHでは、建物の中で使用する空調、照明、給湯、換気の各設備機器を省エネ性能の高いものを設置し、消費エネルギー量の削減を図ります。具体的には省エネエアコン、LED照明、エコキュートやエコジョーズといったの高効率給湯器、熱交換換気の換気設備などが該当します。また、省エネ設備の導入は光熱費の削減にもつながります。
創エネは文字通り、エネルギーを創ること。再生可能エネルギー設備の中でも、太陽光発電システムを設置するケースが多く、蓄電池も併せて備えるのが一般的です。余った電力は電力会社に売ることもできますが、蓄電池に貯めておくと、曇りや雨など天気の悪い日や夜間に貯めておいた電力を使えます。また、蓄電池は災害時の備えとしても有効です。
ZEHでは、創エネによって創り出すエネルギー量が、一次エネルギー消費量を上回るように設計します。

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」
詳しくはこちら>>
資源エネルギー庁の資料によると、ZEHは『外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅』と定義されています。
また、ZEHには定義となる4つの基準が設けられています。4つの基準のそれぞれの条件についてみていきます。
引用:資源エネルギー庁 ZEHフォローアップ委員会「ZEH+の「外皮性能の更なる強化」の暫定措置の今後の取扱いについて」
1つ目の基準は「高断熱」に関わり、1~8の地域区分により決められた強化外皮基準のUA値が0.4~0.6以下であること。これは平成28年(2016年)省エネルギー基準よりも厳しい水準です。
<地区別強化外皮基準>(UA値)
| 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 |
| 0.4以下 | 0.4以下 | 0.5以下 | 0.6以下 | 0.6以下 | 0.6以下 | 0.6以下 | - |
代表的な都市を挙げていくと、1地域は旭川、2地域は札幌、3地域は盛岡、4地域は仙台、5地域は新潟・筑波、6地域は東京・名古屋・大阪、7地域は宮崎・鹿児島、8地域は那覇が該当します。
* 外皮性能とは?
まず、外皮性能の外皮とは、建物の室内外を隔てる外壁や窓、屋根・天井、床などを指します。そして、外皮性能とは外皮の断熱性能のことです。
外皮性能は、外皮平均熱貫流率(UA)と冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)の2つの指標によって評価されています。外皮平均熱貫流率(UA)は、室内外の熱の出入りのしやすさを示す指標です。冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)は、冷房期の室内への日射の入りやすさを示す指標をいいます。
2つ目の基準は「高断熱」と「省エネ」に関わるもので、目標水準となる基準一次エネルギー消費量より、一次エネルギー消費量を20%以上削減すること。この項目では、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備による創エネは考慮せずに計算します。
断熱材の使用や断熱性能の高いサッシ・ガラスの設置による高断熱化により、必要なエネルギー量を削減できます。また、エネルギー効率の高い空調設備や、照明器具、給湯設備、換気設備を設置し、一次エネルギー消費量を削減します。
3つ目の基準は「創エネ」に関わるもので、再生可能エネルギーの導入です。ZEHでは、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備の導入が必須となっています。ただし、再生可能エネルギー設備によって創出されるエネルギー容量に関する規定は設けられていません。
広義のZEHでは、再生可能エネルギー設備の導入が必須ではないZEH OrientedもZEHに含まれます。ただし、創エネが難しい都市部の狭小地や多雪地域が対象となっています。
最後の4つ目の基準は、「高断熱」「省エネ」「創エネ」のすべてに関わるものです。基準一次エネルギー消費量から、再生可能エネルギーを含めて、一次エネルギー消費量の100%以上の削減が基準です。
一次エネルギー消費量から太陽光発電システムなどによって創ったエネルギー量を差し引いて0以下になれば、基準一次エネルギー消費量を100%以上削減したことになります。つまり、一次エネルギー消費量が実質ゼロ以下という状態です。

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」
詳しくはこちら>>
住宅の省エネ性能の基準には、公的な省エネ基準やZEH基準以外にも、HEAT20による基準があり、省エネ住宅や高断熱住宅に関心を持つ人などに注目されています。それぞれの基準について概要を紹介したうえで、違いについて考えていきます。
省エネ基準とは、建物が備えるべき省エネ性能を確保するために定められた建築物の構造と設備に関する基準です。省エネ基準は、省エネ法の改正によって改定が行われ、現行の平成28年省エネ基準は、2016年4月に一部施行・2017年4月に完全施行された建築物省エネ法にもとづいています。
省エネ基準は、一次エネルギー消費量基準と外皮基準からなります。
一次エネルギー消費量基準は、一次エネルギー消費量が基準値以下となることが求められます。一次エネルギー消費量は「空調エネルギー消費量」「換気エネルギー消費量」「照明エネルギー消費量」「給湯エネルギー消費量」「昇降機エネルギー消費量(非住宅用途のみ)」「その他エネルギー消費量(OA機器等)」の合計から「太陽光発電設備等による創エネ量(自家消費分)」を引いて算出します。
外皮基準は住宅にのみ適用されます。外皮総熱損失量を外皮総面積で割って算出した外皮平均熱貫流率(UA)が基準以下となることが求められます。
ZEH基準は、前述した4つの基準が設けられています。1つ目は、地域区分により定められた強化外皮基準UA値0.4~0.6以下であること。2つ目は平成28年省エネ基準である基準一次エネルギー消費量より、一次エネルギー消費量を20%以上削減すること。3つ目は、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備を導入すること。4つ目は、再生可能エネルギーを差し引いて、基準一次エネルギー消費量から一次エネルギー消費量の100%以上の削減です。
ZEH基準は、建物で使うエネルギー量から太陽光発電システムなどによってつくったエネルギー量を引くと0以下となる基準です。
HEAT20とは、「一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」の略称・故障です。2009年に住宅・建材生産者団体の有志によって、2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」として発足し、2020年に一般社団法人に移行しました。
HEAT20では、住宅外皮水準G1~G3を設定。地域区分ごとに室温(NEB)とエネルギー(EB)でそれぞれ2つずつの指標を設定し、4つの指標による住宅シナリオを満たすことを目標としています。
室温(NEB)は、暖房期の最低室温による指標と、室内が15℃未満になる時間・面積の割合による指標が設けられています。エネルギー(EB)では、平成28年省エネ基準からの暖房負荷削減率と全館連続暖房時の暖房負荷増減率による指標があります。
たとえば、G1の家の基準をみていくと、1・2地域では冬期間の室温がおおむね13℃を下回らず、室温が15℃未満となるのが3%程度、平成28年省エネ基準の家に対する暖房負荷削減率は20%です。3~7地域では、冬期間の室温がおおむね10℃を下回らず、室温が15℃未満となるのが3地域は15%程度、4~7地域は20%程度。平成28年省エネ基準の家に対する暖房負荷削減率は30%です。
参照:一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会「HEAT20の家─手に入れよう豊かなくらし」
省エネ基準とZEH基準を比較すると、ZEH基準は一次エネルギー消費量基準と外皮平均熱貫流率(UA)のいずれも、省エネ基準よりも厳しい基準が設けられています。
また、HEAT20による住宅外皮水準G1~G3のいずれも、省エネ基準やZEH基準よりも厳しい基準となっています。
ただし、省エネ基準やZEH基準では、外皮平均熱貫流率UA値を満たすことが、基準の一つとなっていますが、HEAT20では外皮平均熱貫流率UA値は目安として位置づけているという違いがあります。HEAT20が目指すのは住宅シナリオと呼ばれる基準です。
ZEH基準を超える高断熱住宅を建てたい場合は、HEAT20による住宅外皮水準G1~G3を目指すという方法もあります。

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」
詳しくはこちら>>
省エネ性能の高いZEHは、光熱費の削減が見込めるほか、健康で快適な暮らしが送れる、蓄電池が非常時の備えとなるといったメリットがあります。また、資産価値が維持できる可能性があることも、ZEHの魅力です。
ZEHはエネルギー効率のよい設備を設置しているため、光熱費を削減できます。また、高断熱仕様により、冷暖房などにかかる光熱費の削減につながります。
さらに、太陽光発電システムによる自家発電によって、電力会社から買う電気使用量が減ります。また、余剰電力を電力会社に売却することで収益化が見込めることもメリットに挙げられます。
ZEHは断熱材の使用や高い断熱性能を持つサッシやガラスの設置により、室内が外気温の影響を受けにくくなります。夏は涼しく、冬は暖かい快適に過ごせる環境を得られるというメリットがあります。また、冬場には冷たい外気が伝わりにくいため、結露の発生も抑制できます。
ZEHでは、太陽光発電システムと蓄電池をセットで設置するのが一般的です。蓄電池で日中に余った電力を貯めておくほか、電気代が安い時間帯に充電しておくと、災害などによる停電時に、非常用電源として活用できるというメリットがあります。
ヒートショックによる脳卒中や心筋梗塞は、入浴時に暖かいリビングから、寒い洗面脱衣室や浴室に移動し、温かいお風呂に入るなど、急激な温度変化によって血圧が上下するのが原因です。ZEHは高断熱仕様により、外気温の影響を受けにくいことから、部屋ごとの温度差が少なくなり、ヒートショックのリスクの軽減につながります。
また、結露を抑制できれば、カビやダニによるアレルギーのリスクを軽減できます。
ZEHは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会による「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」の認証を取得し、第三者機関によって省エネ性能の客観的な評価を受けることで、資産価値を高く保てる可能性があることもメリットに挙げられます。BELSでは、一次エネルギーの消費量が、1つ星から5つ星の5段階で評価されます。
これにより、類似する立地条件や築年数、広さの物件と比較して、将来的に高値で売却できる可能性があります。

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」
詳しくはこちら>>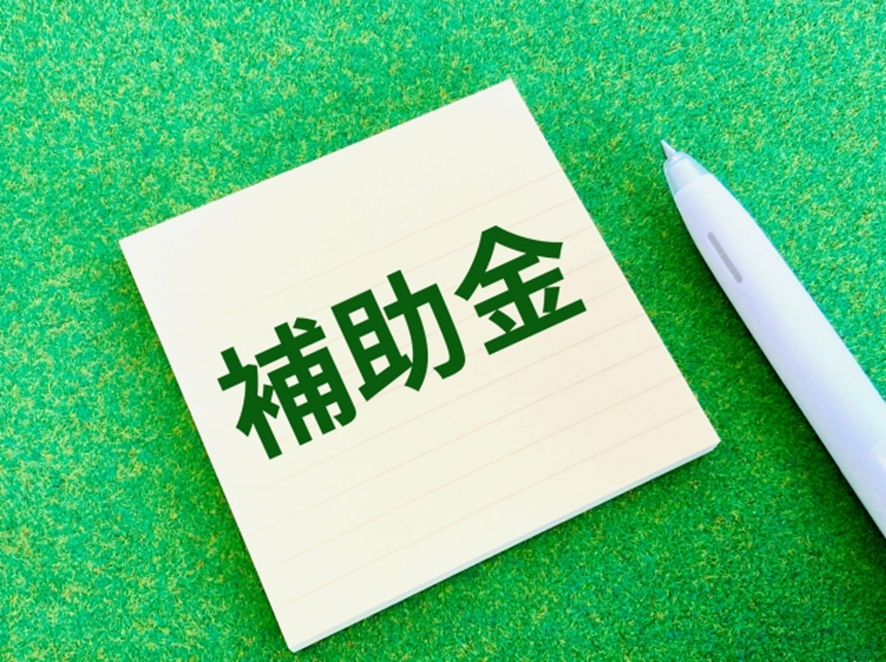
2024年度は、経済産業省と環境省によるZEH支援事業が実施されています。
ZEH支援事業による補助金の申請を行うには、SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)に登録されているZEHビルダー・ZEHプランナーである事業者が設計や建築を行うことが条件の一つとなっています。
また、補助金の申請期間が決められており、交付決定後に着工するなど、規定されたスケジュールや手順に沿って進めていく必要があります。予算枠があり、先着方式で要件を満たしている住宅の事業から採択されます。
ZEH支援事業には「ZEH」と「ZEH+」の区分があり、対象や補助金の額などが異なります。
「ZEH」の区分は、ZEHとNearly ZEH(寒冷地・低日射地域・多雪地域のみ)、ZEH Oriented(都市部狭小地等の二階建以上・多雪地域のみ)が対象。「ZEH」の区分の補助金は55万円です。
「ZEH+」の区分は、ZEH+とNearly ZEH+(寒冷地・低日射地域・多雪地域のみ)が対象です。「ZEH+」の区分の補助金は100万円。要件を満たしていると支給される追加補助額として、ハイグレード仕様補助金が設けられ、25万円、または10万円です。
また、「ZEH」と「ZEH+」と共通の追加設備による加算が設けられています。「蓄電システム」は上限20万円、「直交集成板(CLT)」は定額90万円、「地中熱ヒートポンプシステム」は定額90万円。このほかには、「PVTシステム」や「液体集熱式太陽熱利用システム」も加算の対象です。
参照:一般社団法人環境共創イニシアチブ「2024年の経済産業省と環境省のZEH補助金について」
ZEH住宅の補助金制度については、以下の記事で詳しく解説しています。
▼『ZEH(ゼッチ)住宅とは?補助金の条件やメリット・デメリットをわかりやすく解説【2024年版】』

理想の住まいをワンストップで実現できるリノベーションサービス「MyRENO マイリノ」
詳しくはこちら>>ZEHは省エネ基準を上回る厳しい基準を満たした省エネ住宅です。厳密にいうとZEH住宅には4つの基準が設けられていますが、端的にいえば、「高断熱」「省エネ」「創エネ」により、一次エネルギー消費量が実質ゼロになる家を指します。
光熱費の削減や収益化が見込まれるほか、健康的で快適に過ごせる、災害時の停電対策になるといったメリットがあり、補助金制度も設けられています。
ZEHの基準や特徴を理解したうえで、家づくりについて考えてみましょう。
マイホームをZEHにするには、新築住宅を建てる方法のほかに、中古物件を購入してリノベーションするという方法もあります。
グローバルベイスでも、ZEH水準リノベーションを行っています。東京都渋谷区の区分所有マンションの一室でZEH-Oriented基準の省エネ改修を実施。BELSにおける省エネ性能の最高評価の5つ星を取得した実績があります。
グローバルベイスは設計力やデザイン力に定評があり、スタイリッシュなデザインでありながら、機能性が高く快適な住まいを実現できます。